











旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。












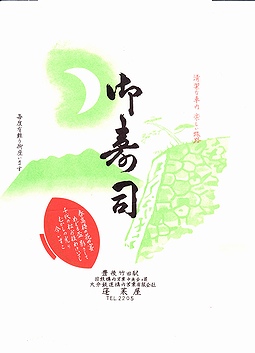
1960年代のものと思われる、昔の豊後竹田駅弁の掛紙。ここに描いた月と山と石垣は、荒城の月と九重山と岡城か。この当時から列車の到着時に駅で流していた、瀧廉太郎のメロディーのイメージか。赤い盃に記される歌詞は竹田のものでなく、土井晩翠の宮城県仙台などのイメージといわれる。


これは駅弁でなく、港で買えたお弁当。愛媛県の三崎と大分県の佐賀関を結ぶ国道九四フェリーの、佐賀関港フェリーターミナルの土産物店で買えた。港の弁当とは名乗っていない。黒いプラ製トレーに、白飯ととり天と千切りキャベツと沢庵を盛り付ける、まるでスーパーの惣菜弁当。この鶏肉の天ぷらは大分の郷土料理であるから、大分の港の弁当として、旅行者が買って感心する弁当にふさわしい。この大分県の佐賀関港で売られるほか、フェリーに乗って愛媛県の三崎港の切符売り場でも販売される。調製元はフェリー会社そのもの。
三崎港と佐賀関港を結ぶ航路は、1969(昭和44)年4月に日本道路公団が運航を開始。四国と九州を海路にて最短で結び、所要時間はわずか70分。しかしいずれの港も街から遠く、特に三崎は細長い佐田岬半島の端で陸路に恵まれず、長らく一日3往復の運航だった。宇和島や八幡浜と臼杵や別府を結ぶ航路や、宿毛と佐伯を結ぶ航路に比べ、細々と運航されていたようにみえる。
平成時代になると道路事情が格段に良くなり、佐田岬半島の横断時間が約2時間から1時間以内に半減、大分県にも高速道路が通じた。国道九四フェリーの経営となった航路は増便を重ね、今では7時台から23時台まで毎時に出る一日16往復もの運航。それでも訪問時には自動車を積み残す賑わいだった。宇和島や宿毛からは九州行の船が消え、今ではここがメインルート。
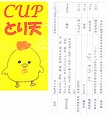

これは駅弁でなく、港で買えたお惣菜。愛媛県の三崎と大分県の佐賀関を結ぶ国道九四フェリーの、佐賀関港フェリーターミナルの土産物店で買えた。鶏肉の天ぷら、大分名物のとり天が、飲料向けのプラ製カップに、収まるだけ詰められる。このような惣菜は大分ではありふれていて、過去に別府駅でも買えたことがある。これも調製元はフェリー会社。
四国と九州の移動は、自動車があればフェリーが便利だが、鉄道はなく、福岡発着の夜行高速バスやJAL航空路が数便あるくらい。松山から一日3便、八幡浜から一日2−3便の三崎行きバスの時刻を見定めて、佐賀関で毎時1本程度あるはずの大分行き路線バスを捜索すると、4−6時間の行程となる。または、駅から遠い遠い八幡浜港と別府港の位置を頑張って調べれば、片道3時間または夜行の宇和島運輸フェリーが一日6往復。時刻表の読者であれば一度は計画する行程も、この位置で四国と九州を移動する理由は作りにくいと思う。今回はその両航路に乗ることを目的として、30年越しの移動を実現し、観光客のいない船旅を楽しんだ。

これは駅弁でなく、鉄道銘菓とも言い難いが、大分の菓子に鉄道の駅と列車を組み合わせており、駅売りが考えられるので収蔵。薄焼きの黒ごま小麦粉せんべいが14枚、個別包装で入っている。2008年に姫路へ多くの観光客を集めた第25回全国菓子大博覧会で、名誉総裁賞を獲得したそうな。あまり知られていない大分の郷土料理で、小麦粉を使ったおやつ「やせうま」を焼いたものだろうか。
掛紙には、1989(平成元)年3月に博多駅〜由布院駅〜別府駅で運行を始めた観光客向け特急列車「ゆふいんの森」と、1990(平成2)年12月に竣工した由布院駅の駅舎を描く。1987(昭和62)年4月の分割民営化で国有鉄道から転換したJR九州が、古い急行形気動車の車体を深緑色のオールハイデッカーに載せ替えたり、有名デザイナー仕様でギャラリーを備えて改札口を廃した駅舎を建てたもの。鉄道の営業の常識を疑うこの試みは、バブル経済の頃に大いに注目された。
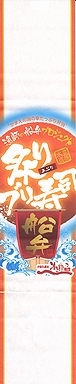

これは鉄道の駅弁でなく、国道388号沿いの「道の駅かまえ」で販売されていたお総菜。駅弁、空弁、速弁に次ぐ「船弁」として開発したといい、商品名を描いた紙帯に船弁と2回書く。中身は四角い棒状の酢飯に、地元の養殖ブリの薄切りを炙ったものを貼り合わせたもの。煮たり生で食べることが多い魚の、また違った香りと食感を楽しめた。
調製元は、蒲江の漁師が10人集まり国と県の補助金を得て2005年に立ち上げた食品加工販売業者。「漁師の船弁プロジェクト」としてブリやヒラメを使った弁当を開発し、道の駅やイベントなどで販売しているという。
1974(昭和49)年2月指定の日豊海岸国定公園は、大分県南部と宮崎県北部にまたがる、太平洋と瀬戸内海との間にある豊後水道に面したリアス式海岸。翌年に国道に指定された国道388号がここを縦貫するが、公共交通機関の足はほとんどなく、時刻表で旅をする限り訪れる機会を持てない。そもそも、豊後の国の大分県と日向の国の宮崎県は、時刻表を見ても分かるとおり交流が少ない。訪れてみれば良い魚と地形と海があるのに、ここへ旅に出たという話をさっぱり聞かないのは、すこしもったいないと思った。
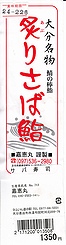

これは鉄道の駅弁でなく、大分自動車道湯布院インターチェンジの出口真正面にある「道の駅ゆふいん」で買えた、道の駅弁のようなもの。酢飯とサバを貼り合わせて8切れにカットした焼きサバ寿司が、ラップと竹皮に包まれる。小柄なのに、なかなかの値段。価格の札に切れ目を入れたことから、道中の弁当というよりはむしろ、土産物として売るのだろう。