











旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。














2024(令和6)年11月16,17,23,24日の7時30分から、伊勢原駅の改札内コンコースで販売。小田急電鉄の相模大野管区と伊勢原市内の飲食店とのコラボ企画として、駅での「おおやま彩りごはん」の販売を実施した。ネット上で伊勢原駅弁を販売するという投稿もみられた。現地に行くと調製元は2店あり、3種類の弁当を、紅葉の最盛期で大山へ向かう観光客を相手に販売していた。伊勢原の駅弁を作ろうという試みは、過去にも地元やお祭りの場ではあったらしい。
惣菜や創作で使われがちなタイプの紙容器に、大山の紅葉やススキ野と伊勢原駅舎を描いた掛紙を巻く。掛紙には調製元の名と「小田急駅員」が記される。中身は玄米の日の丸御飯と、冬瓜(とうがん)入りハンバーグ、鶏のグリル、天然秋鮭のグリル、さつまいもの塩麹あえ、玉ねぎステーキ、もものすけ・三種のパプリカのグリル、人参しりしり。同じ容器と掛紙と価格を共有する、白米のものもあった。調製元は伊勢原市街で不動産業者が経営すると思われる小さな食堂。
伊勢原(いせはら)は、神奈川県の真ん中にある市。丹沢山地や大山の山麓に農村ができ、江戸時代には伊勢の国からの開拓団により伊勢原の地名が付き、大山寺の参詣で賑わい街道ができた。1927年に鉄道が通じ、1960年代に国道が改良され高速道路が開通、工場や住宅が進出して市制を敷く10万都市になり、伊勢原駅の利用者は一日5万人にも及んだ。
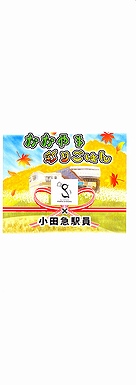

2024(令和6)年11月16,17,23,24日の7時30分から、伊勢原駅の改札内コンコースで販売。小田急電鉄の相模大野管区と伊勢原市内の飲食店とのコラボ企画として、駅での「おおやま彩りごはん」の販売を実施した。ネット上で伊勢原駅弁を販売するという投稿もみられた。現地に行くと調製元は2店あり、3種類の弁当を、紅葉の最盛期で大山へ向かう観光客を相手に販売していた。伊勢原の駅弁を作ろうという試みは、過去にも地元やお祭りの場ではあったらしい。
惣菜や創作で使われがちなタイプの紙容器に、大山の紅葉やススキ野と伊勢原駅舎を描いた掛紙を巻く。掛紙には調製元の名と「小田急駅員」が記される。中身は伊勢原産赤米ごはんに電車型の海苔を載せ、野菜たっぷり厚焼き卵、伊勢原名物鳥酢、神奈川県産さつま芋の甘煮、ミニトマトとブロッコリー。調製元は伊勢原駅近くのカフェバーレストランで、鳥酢は人気のメニューだという。
伊勢原駅は、大山への公共交通での玄関口。電車が10分毎、バスが毎時2〜4本発着し、ハイキング客が通年で訪れる。第二次大戦後には平塚から伊勢原を経て大山山頂まで、トロリーバスとロープウェイとケーブルカーを乗り継ぐルートが提案されたほど。そんな駅なのに観光の要素がなく、小田急電鉄の特急ロマンスカーの停車は2016年まで実現せず、駅も駅前も古くて狭く、観光客が使えるようなお店も見あたらず、駅弁もない。大山や丹沢の観光が廃れることはないと思うので、頓挫し続ける駅前再開発が実現してよくなるか、駅のコンビニチェーン店かコーヒーチェーン店のブランドが変わり駅弁を置いてくれるようになるか。
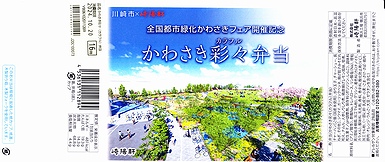

川崎市での「全国都市緑化フェア」の開催を記念し、川崎市と調製元の2度目のコラボレーション企画として、2024(令和6)年10月19日から23日まで、川崎、新川崎、武蔵小杉の各駅を含む川崎市内の11店舗で販売。他に店頭予約により神奈川県内の約100店舗でも販売。掛紙にはその富士見公園での開催のイラストが使われた。容器と中身は、下記の2022年のものと同じ。これに対して「環境に配慮した紙カップ、紙蓋、木製折り箱、木製フォークを使用」という解説が付いたが、横浜の駅弁では日常なので気にならない。
全国都市緑化フェアは、旧建設省の財団法人が1983(昭和58)年から毎年1回か2回開催する地方博覧会。都市緑化の意識の高揚、都市緑化に関する知識の普及等を図ることにより、国、地方公共団体及び民間の協力による都市緑化を全国的に推進し、緑豊かな 潤いある都市づくりに寄与する、花と緑の博覧会だそうな。川崎市では第41回として、2024年10月19日から11月17日までと、2025年3月22日から4月13日まで、川崎区の富士見公園、中原区の等々力緑地、多摩区の生田緑地で、草花の展示やステージイベントなどが実施される。
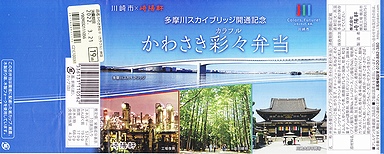

東京都大田区と神奈川県川崎市を結ぶ、多摩川では最下流の橋梁「多摩川スカイブリッジ」の開通を記念して、調製元と川崎市のコラボレーションにより、2022(令和4)年3月12日から4月25日まで、川崎、新川崎、武蔵小杉の各駅など川崎市内の崎陽軒11店舗で販売。これらの駅には昭和時代から崎陽軒の駅弁売店があり横浜駅弁が売られるが、川崎限定の駅弁は過去に聞いたことがなく、もしかすると史上初の川崎駅弁かもしれない。駅弁の名前は「かわさき彩々弁当」で「かわさきからふるべんとう」と読ませる。
かながわ味わい弁当と同じ大きさの容器に、表面に多摩川スカイブリッジと川崎市の観光名所の写真を、裏面に中身のカラー写真に説明と挨拶文を記した掛紙を巻く。小さくも松花堂タイプな4区画の中身は、炒飯、人参しりしり煮と鶏唐揚とシウマイ2個、揚げ餃子2個とナムル、ガーリックペンネとタケノコ煮と抹茶わらび餅。中身と川崎との関連がよくわかるものの、もともと川崎には食の名物がほとんどない、少なくとも隣接する東京や横浜に対する独自のものは川崎大師の葛餅(くずもち)くらいしかないので、考案は大変だったのではないかと思う。普通にいただける、崎陽軒や横浜駅弁の味。
川崎市は、神奈川県の北東端で多摩川沿いに広がる、人口150万人以上の住宅地。多摩川沿いの農村に、江戸時代までに東海道など市域を貫く街道にいくつかの宿場ができ、明治時代にはいち早く鉄道が貫き駅ができ、20世紀に入ると全国有数の臨海工業地帯が形成された。戦後昭和時代以降は東京のベッドタウンとして都市鉄道の敷設や住宅地の開発が進み、今に至る。
これだけの大都市であるにもかかわらず、駅や駅弁では影が薄い。市の名になる川崎、川崎駅や川崎区が市の中心になるはずが、鉄道も高速道路も個別に東京へつながり、川崎が拠点にならない。日本の鉄道と同じ長さの歴史を持つ川崎駅は、国鉄が1969年に特定都区市内制度を導入してから現在まで運賃制度上はなんと横浜の一員であり、1970年代に崎陽軒が進出するまで駅弁もなく、1980年まで普通列車にも通過されたような駅であった。高度経済成長期の公害のイメージが払拭され、そのうち独自の食や駅弁で東京や横浜から客を呼べるような時代が、訪れるかどうか。
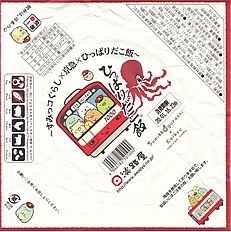

2020(令和2)年1月16日から22日まで、神奈川県横浜市の京急百貨店で販売。同店の「全国有名直送駅弁大会」で、京浜急行電鉄とタイアップ中のサンエックスのキャラクター「すみっコぐらし」にちなみ、兵庫県の西明石駅弁「ひっぱりだこ飯」にそのキャラクターを加え、地下食料品売り場で輸送販売した。駅弁大会の規模そのものは、小さなスーパーと変わらない程度。
陶製のタコ壷容器は通常版と同じで、掛紙に京急新1000形電車と、「すみっコぐらし」に登場する様々なキャラクターを描く。醤油飯をタコ煮、菜の花、刻み煮穴子で覆い、揚げかまぼこを仕込む中身は通常版と同じで、これに設定上人気者だというたこウインナーを加えた。
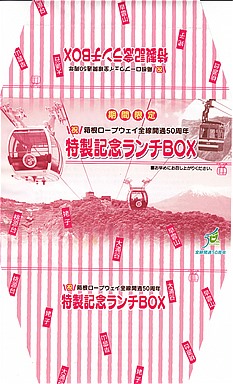

箱根ロープウェイの全線開通50周年を記念して、2010(平成22)年4月24日から2011(平成23)年3月31日までの予定で販売した、世にも珍しいロープウェイの駅弁。早雲山駅と大湧谷駅に加えて、箱根登山鉄道の箱根湯本駅でも販売された。
環境に配慮して採用したという牛乳パック素材の紙箱を、ロープウェイの写真を掲載した赤インク単色の掛紙で巻く。地産食材を使用したという中身は、野菜たっぷり豆腐ハンバーグサンド3切れ、箱根山麓豚のボロネーゼ・パスタ、地元農家のお野菜ピクルス、自家製ダレに漬込んだ煮たまご半個。見た目も内容もスパゲティを除く味も洗練されている印象。
箱根ロープウェイは、小田急電鉄の子会社が1959(昭和34)年と1960(昭和35)年に分けて早雲山から桃源台まで4,005メートルの区間で開業したロープウェイ。西武鉄道と小田急電鉄が箱根の観光開発で激しく対立した通称「箱根山戦争」により、西武系の駿豆鉄道(現在の伊豆箱根鉄道)が所有していた道路でのバス運行を閉め出された小田急側が、芦ノ湖への足として空中で対抗したものである。
今では年間200万人の利用者で賑わい、シーズンには1時間以上の待ち行列ができたり、2009年にはギネスブックに掲載されるなど、道路渋滞を尻目に箱根の交通を支える。2000年から2007年にかけて掛紙写真のような「フニテル」タイプに掛け替えて、弱点であった強風による運休日の減少を図った。
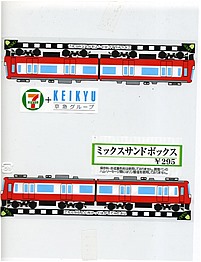

コンビニエンスストア大手であるセブンイレブンの、近所の店舗で買ったコンビニサンド。白いトレーと透明なふたがつながったプラ製容器に、細長いタマゴサンドとツナサンドとハムチーズレタスサンドを2切れずつ収める。中身や風味そのものはコンビニサンドそのものであり、写真を撮って収穫と名乗るものではないが、パッケージを包むフィルムに京浜急行電鉄の電車のイラストが描かれていたから、駅弁に準じる駅弁サンドに見えてきた。
購入店は京急の駅構内でも沿線でもないが、2009年9月30日にセブンイレブン・ジャパンと京浜急行電鉄は業務提携に関するニュースリリースを発表し、京急の駅売店「京急ステーションストア」をすべてセブンイレブンに転換することになったので、これに絡んでこんな商品が出てきたものと想像する。調製元はマルハニチロの子会社である湘南フレッシュデリカと書いてあったが、コンビニサンドなので地域ごとにいろんな会社で作っているはず。いつまでこの姿で売られたのだろうか。


プロサッカーリーグ「Jリーグ」の、横浜F・マリノス戦開催時の三ツ沢球技場で、物売りテントで買えたサンドイッチ。ここではマリノスカラーと呼ばれる赤白青のトリコロール色の紙箱に、首都圏ではおなじみのさぼてんひれかつサンドが3切れ入っている。割高感は強いが、観戦の記念ということで。
1993年のサッカーJリーグ開始時の10チームの中で、横浜には日産自動車がスポンサーの「横浜マリノス」と、全日空と佐藤工業がスポンサーの「横浜フリューゲルス」の2チームが立ち、同じ三ツ沢をフランチャイズとした。しかしその後の佐藤工業の経営不振と全日空の経営悪化により、1999年にフリューゲルスはマリノスに吸収合併。チーム名のうち「F」はこんな事情で付いたもの。
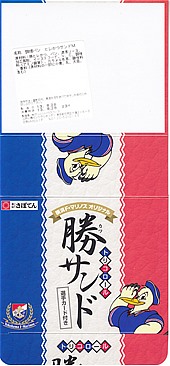

上記の商品「横浜F・マリノスオリジナル勝サンド」の、2013(平成25)年時点での姿で、こんどは日産スタジアムで購入。名前がちょっと長くなり、箱に横浜F・マリノスのキャラクター「マリノス君」が描かれるようになり、選手カードが1枚入るようになった。中身は引き続き、とんかつ新宿さぼてんのヒレかつサンド。
日産スタジアムは、1998(平成10)年3月に「横浜国際総合競技場」の名称で開場。同年の第53回国民体育大会秋季大会「かながわ・ゆめ国体」の主会場となり、2002(平成14)年のサッカーW杯では決勝戦を含む3試合の会場となった。さらに2008(平成20)年の横浜オリンピックのメインスタジアムにしようとしたが、この夢は早々と潰えている。2005(平成17)年からはネーミングライツを日産自動車が取得し、現在の名称に差し替えられた。7万人以上を収容する大きな器を、普段は持て余しているように見えるが、注目を集めるサッカーの試合やコンサートなど、年に1回くらいは威力を発揮する。

J2リーグの試合時に三ツ沢球技場で買えた商品。神奈川県高座郡寒川町が2010(平成22)年から推進するB級グルメ「さむかわ棒コロ」が1本、紙製のパッケージに収まる。さむかわ棒コロとは、町が「ライスペーパー(生春巻きの皮)を使用すること」「ジャガイモを使用すること」「具材にしっかり味を付けること」「できるだけ20センチ位の棒状にすること」「カットして提供する場合には、できるだけ揚げたての棒状を見てもらいビックリさせること」と定義するコロッケ。食べた感想としては、衣が固くしっかりした、棒状のお総菜。

J2リーグの試合時に三ツ沢球技場で買えた商品。小柄なプラ製の惣菜容器に、チャーハンと鶏唐揚3個と紅生姜を詰める。冷凍食品とたいして変わらない、普通の炒飯と唐揚。
この日の試合は、横浜FC対カマタマーレ讃岐。試合は4対2で横浜FCの勝利。後半43分にFW三浦知良が今季初出場、これが自身の持つJリーグ最年長出場記録を47歳5か月22日に更新したと、翌日のスポーツニュースになった。

2005(平成17)年6月25日の横浜市営地下鉄新羽車両基地公開「はまりんフェスタ2005in新羽車両基地」で販売されたお弁当。横浜市営地下鉄マスコット「はまりん」のシールを貼っただけのビニール容器に、日の丸御飯と鶏や蓮根の揚げ物と肉団子と煮物数点や玉子焼にサラダなどを詰める。地下鉄の運転士や車掌が普段食べている弁当だそうな。容器も中身も見た目も風味も、駅弁ともオフィス向けランチとも呼べない、完璧な事業所向け調製弁当。体育会系な男性職場の雰囲気を感じる。調製元は不詳。なお、その後の横浜市営地下鉄での車両基地公開イベントでは、このような弁当の販売を見ていない。新羽車両基地で実施された時には、横浜駅弁の崎陽軒がテントを出していた。
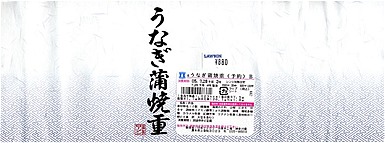

コンビニ大手のローソンが、2005(平成17)年の夏に販売したウナギ弁当。コンビニらしい平たく上げ蓋のプラ容器に掛紙を巻いて食品表示ラベルを貼る。中身は見てのとおりの鰻重。工業製品風だが、鰻蒲焼やそのタレに御飯の風味や品質は水準を保っており、外観も価格も風味も、駅弁の領域に侵食しているのではと思う。しかしコンビニ弁当の宿命で、商品寿命は数週間程度だった。
当館はコンビニ弁当を収蔵の対象としない。しかし、駅弁側あるいは駅弁ファンから見て、不味いだの風情がないだの添加物漬けだの、さんざん非難されるコンビニ弁当も、長年に渡る過剰とも言える熾烈な競争と品種改良により、今や駅弁と価格も風味も同等あるいはそれ以上の商品も出ていることを、ここに記録しておく。ここでの製造元は日本水産の子会社で本州と九州に9工場を構える、ローソンを得意先とする惣菜製造販売業者。



東京駅から東海道線の電車で約1時間。平塚市は神奈川県の中部で相模湾に面して相模川が流れる、人口約26万人の宿場町。江戸時代に東海道の平塚宿や徳川家別荘の中原御殿があり、関東大震災や空襲に遭うもその前後に工業が集積、第二次大戦後は商業や住宅地で発展し、神奈川県央の主要都市となる。駅弁は香魚軒が1915(大正4)年から1980年代まで販売、その後は駅弁売店を小田原駅弁の東華軒や大船駅弁の大船軒が引き継いだが、2020年までに閉店した。1887(明治20)年7月11日開業、神奈川県平塚市宝町。