











旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。












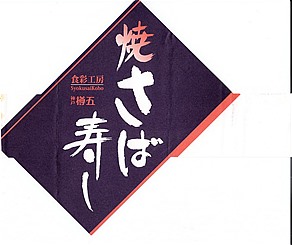

これは駅弁でなく、明石海峡大橋の淡路島側に位置する淡路サービスエリアで販売されていた土産物。板昆布と笹の葉を貼り大葉と生姜を混ぜた焼サバ寿司が1本、ビニール袋に密封されて市販の白い紙箱に収まり、商品名とブランド名を書いた掛紙が巻かれる。食品表示によると高速道路の商品としては珍しく地元で製造されているようであるが、油漬けでべたべたした残念な印象。調製元は江戸時代創業の海産物卸問屋。
神戸淡路鳴門自動車道は、昭和の頃は瀬戸大橋あるいは本州四国連絡橋の神戸・鳴門ルートと呼ばれていた、淡路島を縦貫して明石海峡と鳴門海峡に長大橋を1本ずつ架けて、本州と四国を、兵庫県と徳島県を結ぶ自動車専用道路。本ルートは世界最長の吊り橋である明石海峡大橋(全長3,911m、支間長1,991m)の完成により1998(平成10)年4月5日に全通した。同日に淡路サービスエリアも開業、駐車場やトイレ、売店やレストランから、ガソリンスタンドや花時計や観覧車まで備える巨大な行楽地になっている。
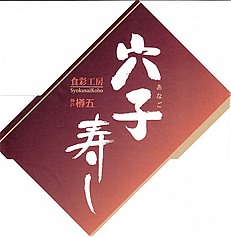

これは駅弁でなく、明石海峡大橋の淡路島側に位置する淡路サービスエリアで販売されていた土産物。小骨が浮き出るワイルドで薄く身の締まった焼きアナゴの棒寿司が1本、ビニール袋に密封されて市販の白い紙箱に収まり、商品名とブランド名を書いた掛紙が巻かれる。少量の割に高価であるが、味付けと食感が硬すぎず柔らか過ぎず、同じ調製元の焼サバ寿司とは雲泥の差。アナゴがいてサバはいない瀬戸内海沿岸では、買う前から選択の方向が見えていたかもしれない。
深夜の1時に訪問した淡路サービスエリアは満員御礼。高速千円とツアーバス盛況のおかげだろうか、過去に鉄道が捨てて駅では失われた深夜の賑わいが、高速道路には存在した。


2014(平成26)年1月の阪神百貨店の駅弁大会で、尼崎駅の駅弁として販売。実際に尼崎駅で売られたかは疑義がある。東京都新宿のキャラクター会社が持つコンテンツ「ちっちゃいおっさん」を名乗り、その絵柄がパッケージの表や裏や横や中に使われる。中身は醤油飯を鶏つくね串と鶏そぼろで覆い、焼き鳥、小松菜、クルミ、ししとう、ニンジン、うずらの卵を添える。小腹あるいは酒の友に良さそうな、味の濃い軽食の味は悪くない。4月頃まで新大阪駅か大阪駅で売られた模様。



姫路駅から山陽本線の電車で4駅15分。駅名から現在の兵庫県たつの市、過去の龍野市や龍野町の玄関口に見えて、その市街から1里以上離れた場所に設けられ、当時計画された鉄道での連絡は実現しなかった。駅弁は当時市販の鉄道時刻表によると1920年の前後に売られ、戦前昭和時代には構内営業者がいた。1889(明治22)年11月11日開業、兵庫県たつの市揖保川町黍田。


姫路駅から山陽本線の電車で約30分。1955年に赤穂市に編入された有年村の玄関口であり、国鉄赤穂線の建設により1951年に廃止された赤穂鉄道による播州赤穂への陸の玄関口でもあった。有年駅に駅弁はないが、戦前昭和時代には構内営業者がいた。1890(明治23)年7月10日開業、兵庫県赤穂市有年横尾。



姫路駅から山陽本線の電車を乗り継いで30分強。上郡町は兵庫県南部の西端にある、人口約1.3万人の町。駅弁は1903(明治36)年から1980年代まで売られ、古くは鮎寿司が名物だったという。1895(明治28)年4月4日開業、兵庫県赤穂郡上郡町大持。