











旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。















広島駅から山陽本線で約30分。国重要文化財で世界文化遺産の厳島神社を抱える、古来から参拝客や観光客を集め日本三景に数えられる宮島への玄関口として、駅が設けられ、鉄道連絡船やフェリーが発着する。駅弁は明治時代からの駅弁屋「うえの」が「あなごめし」1種類のみを百年以上売り続ける。1897(明治30)年9月25日開業、広島県廿日市市宮島口一丁目。


1901(明治34)年に15銭で発売したアナゴ蒲焼き丼。その当時の姿のまま21世紀の現在まで生き残る、駅弁のシーラカンス。多くの駅弁ファンや専門家に、そして多くの雑誌やテレビなどでの駅弁特集で、日本一の駅弁と評価されている。
ふたから底まですべて木製の経木折を、過去に使用された12種類の絵柄をランダムに使う掛紙で包む。この掛紙は「その九」版。中身は餅米を1割混ぜてアナゴの出汁で炊いた御飯の上に、素焼きした後にタレに漬けて焼くことを3回繰り返した白焼き穴子を敷き詰め、タクアン、奈良漬、ガリを添えるもの。出来立ての暖かい弾力のある味よりも、数時間から半日程度常温で放置してなじませた締まりのある味のほうが良いとされる。
一日あたり約500個が売れるといい、繁忙期には予約を断り駅で奪い合われ、調製元の食堂には行列ができるほど。駅弁屋さんは「あなごめし」以外の弁当を取り扱わない。2004年度のJR西日本の駅弁キャンペーン「駅弁の達人」の対象駅弁。価格は長らく1,470円であったが、2014年に1,728円へ一気に値上げ。2016年3月から1,944円。2019年に2,160円となり、同時に1,512円の「ミニ」、1,890円の「小」、2,700円の「特上」が出た模様。2023年時点で「小」2,160円、この「レギュラー」2,430円、「特上」2,970円。2024年時点で「小」2,430円、「レギュラー」2,700円、「特上」3,240円。
宮島口駅ではJR西日本の豪華団体列車「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」の受け入れのため、2016(平成28)年8月までに駅舎内の売店が閉店して駅前へ移動したため、駅で駅弁を買うことができなくなった。名物駅弁「あなごめし」そのものは、その売店であるセブンイレブンと調製元で健在であった。2023年に訪問すると、コンビニでの販売は終了、調製元は満員で繁忙期の弁当販売をとりやめていた。午前中の広島駅ビルであれば買えると思う。
※2025年9月補訂:写真を更新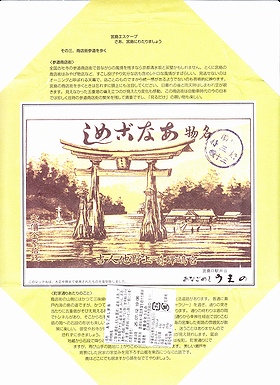

宮島口駅弁のあなごめしの「(大)」版で、2019年に発売か。これは駅でも駅弁の輸送販売や実演販売では買えず、宮島駅前の調製元で繁忙期を除き注文できる。作り置きはしないようで、店頭の弁当窓口で注文して、しばし待つ。掛紙と中身は駅弁のものとまったく同じ。経木折が少し大きく正方形になり、内容量が3割ほど増えた感じで、価格は2割増し。
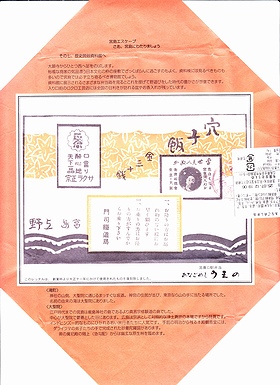

宮島口駅弁のあなごめしの「(小)」版で、2019年に発売か。これは駅でも駅弁の輸送販売や実演販売では買えず、宮島駅前の調製元で繁忙期を除き注文できる。作り置きはしないようで、店頭の弁当窓口で注文して、しばし待つ。掛紙と中身は駅弁のものとまったく同じ。長方形の経木折が2割ほど小さくなった感じで、内容量もそれだけ減り、価格は1割引き。
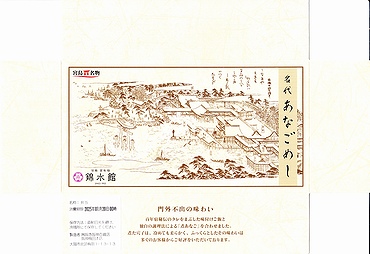

宮島の旅館を名乗るあなごめし。現地でなく、大阪梅田の阪神百貨店で購入。あとで調べると、旅館の紹介に穴子飯はなく、このブランドでネット通販や催事出店を行い、宮島でこの商品を売ることはないらしい。経木折にタレ御飯を詰め、錦糸卵と薄くて柔らかい焼アナゴで覆い、漬物を添えて、宮島神社を描いた掛紙でふたをする。味はどちらかといえば、宮島の島内や港で買ったり食べられる歯応えのあるものではなく、広島駅や福山駅の駅弁のように溶けるような柔らかさのあるものであった。もし2025年1月に阪神百貨店の駅弁大会があれば、そこに出店しただろうか。
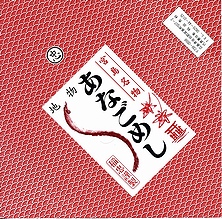

宮島で見つけた、街弁版あなごめし。2008年の訪問時で、宮島の島内で3軒、宮島口の港と駅の間で駅弁屋を含め2軒、あなごめしの弁当での販売があった。細長い経木折をラップで丸ごと包み、ボール紙でふたをして包装紙で包み、商品名を書いた掛紙をかけて輪ゴムで留める。中身は宮島名物あなごめし。蒲鉾のような食感で穴子の臭みが個性的。価格は2008年の購入時で1,300円、同じ包装紙と掛紙を使い分量が多い「(大)」は1,700円。2023年時点で、2,000円と2,300円。
宮島で1島1町を構成した広島県佐伯郡宮島町は、自治省〜総務省が法律と地方交付税で圧力をかけて強力に推し進め、広島県も日本一強力に同調した(県内の市町村数が1/4に減少)、いわゆる平成の大合併によって、2005年に対岸の廿日市(はつかいち)市へ編入されている。宮島が廿日市だと言われてもまだピンと来ないが、現地では歴史的や経済的なつながりが強く、町民の有権者1,804名による住民投票で最も支持を集めた相手先である。
※2023年7月補訂:値上げを追記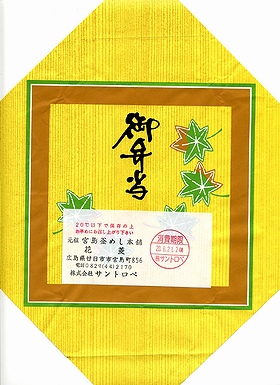

宮島で見つけた、街弁版あなごめし。訪問時には宮島の島内で3軒、宮島口の港と駅の間で駅弁屋を含め2軒、あなごめしの弁当での販売があった。駅弁のような経木折に木目柄のボール紙でふたをして、容器に比して大きめの掛紙で包む。中身は宮島名物あなごめし。干物のような感覚で身を噛むと風味が出る印象。弁当販売の呼び込みは5軒中最もさかんだったと思う。価格は2008年の購入時で1,600円、2023年時点で「宮島名物あなごめし」の赤い掛紙をかけて2,300円。
1996(平成8)年に、宮島の1/7を占める厳島神社のエリアが、ユネスコの世界文化遺産に登録された。1992(平成4)年に日本が世界遺産条約を批准してからの、全国各地での指定獲得競争は、まるでかつての国鉄周遊指定地のそれを思わせる。実際に主目的は観光振興にあるのだろうが、宮島や京都のようなもともと著名で多くの観光客を集めていた観光地では、外国人観光客が以前よりなんとなく多くなったかな、という程度の変化しかないらしい。
※2023年7月補訂:値上げを追記

宮島口で見つけた、街弁版あなごめし。訪問時には宮島の島内で3軒、宮島口の港と駅の間で駅弁屋を含め2軒、あなごめしの弁当での販売があった。駅弁のような経木折に木目柄のボール紙でふたをして、容器に比して大きめの掛紙で包む。中身は宮島名物あなごめし。佃煮のような風味でおこげもある強めの味。価格は2008年の購入時で1,370円、2023年時点で2,160円。
宮島口のある広島県佐伯郡大野町も、平成の大合併により2005年に隣の廿日市(はつかいち)市に編入された。つまり鉄道連絡船として1世紀の歴史を刻む宮島航路は、今では市内航路ということになる。JR西日本と広島電鉄の系列である宮島松大汽船でそれぞれ15分間隔、片道170円、所要時間10分という綱の太さからか、ここに橋を架けたりトンネルを掘ろうという話が全然聞こえてこない。
※2023年7月補訂:値上げを追記