











旅の友「駅弁」。実際に食べた9,000個以上の駅弁を中心に、日本全国と世界の駅弁を紹介します。















新大阪駅から新幹線で約1時間半。広島市は広島県の西側で瀬戸内海に面する、人口約120万人の城下町で政令指定都市。中国地方の商工業の中枢であるほか、世界唯二の被爆都市としてもその名が知られる。駅弁は国鉄時代からの駅弁屋が多種の駅弁を販売するほか、駅ビルで山陽・九州新幹線沿線の駅弁も売られるようになった。1894(明治27)年6月10日開業、広島県広島市南区松原町2丁目。
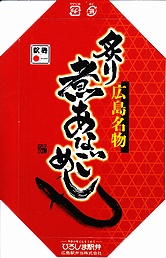

2023(令和5)年1月に広島駅で発売か。下記のとおり「炙りあなごめし」「活あなごめし」など、同じような名前と内容の駅弁が過去に出ているが、「炙り煮あなごめし」という名と赤いふたを持つ広島駅弁は初めて販売か。黒い容器に茶飯を詰め、炙り煮あなごで覆い、広島菜漬けと柴漬けを添える。身は焼あなごより柔らかく、煮あなごよりしっかりした類似品。この内容では宮島口駅弁の次点群に付けられるだろう、おいしいアナゴ駅弁だと思う。

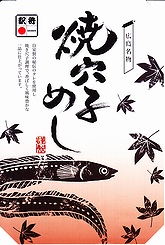

2021(令和3)年までには発売か。公式サイトや時刻表などの駅弁情報に掲載がなく、数少ないネット上の情報もスーパーの駅弁大会での収穫報告しかなく、これも神奈川県のデパートの駅弁大会で買えたものであり、これはきっと催事専用商品なのだろう。中身は下記や宮島口駅などの穴子飯の駅弁と同じく、御飯に焼穴子を並べて覆い、飯にもアナゴにもたっぷり醤油味のたれをかけ、穴子の骨フライと甘酢生姜を添えるもの。だから、食べてまあまあおいしい穴子飯。現存する広島駅弁の穴子飯を見渡すと、これのように広島駅でも売られる宮島口駅弁と穴子飯の部分が同じタイプは無いようなので、もしかすると何らかの事情により現地でなく催事で売られる商品になったのかもしれない。
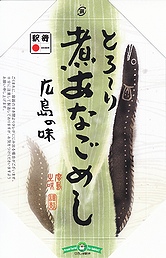

2015(平成27)年に発売か。どうもこの商品は、広島駅でなく東京駅で断続的に販売されている模様。2018(平成30)年10月にJR東日本の駅弁キャンペーン「駅弁味の陣2018」にエントリーし、しかしキャンペーン期間中には首都圏その他JR東日本エリアの駅での販売がなかったので不思議に思った。
商品そのものに不思議はない。以下の広島駅のアナゴ駅弁にとてもよく似た姿。醤油飯を煮穴子で覆い、広島菜の油炒めを添える。味もやはり、名前が違うが見た目が似た下記の駅弁たちと同じような味を持つ、おとなしくうまい駅弁。価格は2019年時点で1,300円、2023年時点で1,450円。
※2023年6月補訂:値上げを追記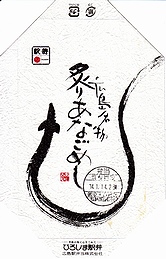

2014(平成26)年1月の京王百貨店の駅弁大会でデビューか。見た目も中身も味も、従前の「活あなごめし」と見分けが付かないくらい似ている。「活あなごめし」が現地版、この炙りあなごめしが駅弁催事版なのかもしれない。茶飯に「炙りあなご」というより煮アナゴを貼り、2種の漬物を添えていた。いずれもとろけておいしい。価格は2014年の購入時で1,260円、2017年時点で1,400円、2023年時点で1,500円。
※2023年6月補訂:値上げを追記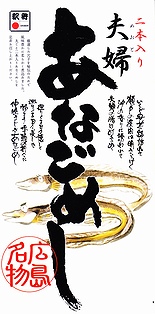

1992(平成4)年に広島駅で発売。現地では「しゃもじかきめし」「もみじ弁当」に次ぐ定番の駅弁で、遠隔地の駅弁催事での輸送販売では「しゃもじかきめし」に次いでよく見掛ける商品。やや小柄で細長めな容器に醤油飯を詰め、煮アナゴ2本を並べて、アナゴの骨の煎餅と高菜を添える。割りばしも中身に組み込まれる。2本のアナゴが寄り添って、夫婦あなごめし。アナゴは薄くて細身ながら、とてもやわらかく、ふっくらしており、これと合う飯に溶け込んでいく。ここや宮島口で人気の焼アナゴの駅弁や弁当とはまた違うタイプの、おいしいアナゴ駅弁。
この駅弁の名前の一部「夫婦」を、「ふうふ」と読むのか「めおと」と読むのか、これまでは活字資料の範囲内では調べることができなかったが、実はそのいずれでもない「みょうと」であることが、2009年に購入した下記の駅弁のふたで判明した。その後、2014年までには「めおと」になったようで、下記の2016年のものはそんな振り仮名に替わっている。価格は2009年時点で1,050円、2014年4月の消費税率改定で1,080円、2015年時点で1,150円、2019年時点で1,180円、2021年時点で1,300円、2023年時点で1,380円。
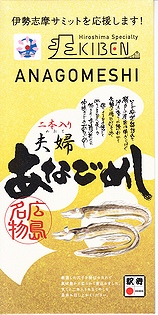
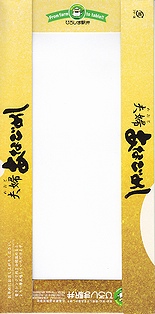

2016(平成28)年5月20日頃の調製と思われる、広島駅弁のパッケージ。伊勢志摩サミットの開催を記念して、仙台駅から小倉駅まで11種類の駅弁について、パッケージに駅弁の名前の英文表記とほぼ共通のロゴマークを印刷し、東京駅の駅弁売店で販売した。価格と中身は通常版と同じ。ここでの「夫婦」のよみがなは「めおと」である。
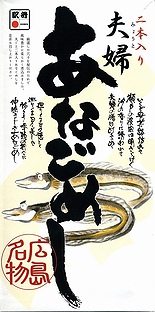

上記の駅弁「夫婦あなごめし」の、2009年時点での姿。上記の2024年のものと、見た目も内容も味も変わらない。当時はふたに記した商品名「夫婦あなごめし」の「夫婦」に、「めおと」でなく「みょうと」の振り仮名をつけていた。
※2024年11月補訂:新版の収蔵で解説文を変更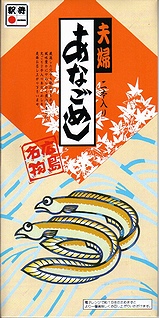

2001(平成13)年12月31日の調製と思われる、広島駅弁のパッケージ。値段と絵柄は異なるが、中身は2009(平成21)年のものと変わらない。
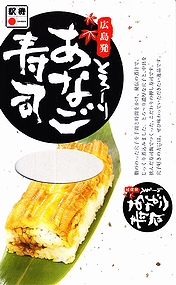

2010(平成22)年1月の京王百貨店の駅弁大会での実演販売で発売か。寿司惣菜向けの細長いプラ容器に、表面にアナゴ煮を貼り、中具にしいたけとかんぴょうの砂糖煮を使う棒寿司を1本、6切れにカットして並べ、ガリとタレを添え、スリーブに収める。食べれば確かな、アナゴの身がとろけるアナゴ寿司。これは駅弁催事専用商品かもしれない。価格は2010年の発売時で1,000円、2015年時点で1,080円、2021年時点で1,200円、2023年時点で1,300円。
※2024年5月補訂:写真を更新


2011(平成23)年1月20日に購入した、広島駅弁のスリーブ。京王百貨店の駅弁大会で購入。本物の笹を使ったり、容器の形やスリーブの絵柄が異なるものの、上記の2024年のものと、品物は変わらない。当時のほうがアナゴの量が多かったと思う。
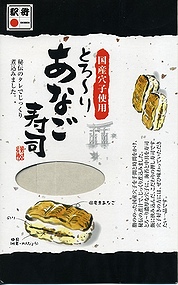


2010年1月16日に購入した、広島駅弁のスリーブ。京王百貨店の駅弁大会でのデビュー作。スリーブの色が異なるが、2011年のものと同じ。内容量は8切れ分あり、同じ価格で量が多かった。
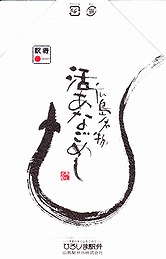

2003(平成15)年の初頭頃に発売か。アナゴの駅弁では日本一と評される宮島口駅の「あなごめし」にそっくりな、広島駅のアナゴ駅弁。商品名とアナゴの墨絵を描いた真っ白なふたをかけた、枠が木でできた小柄な長方形の容器に、アナゴの出汁で炊いた御飯を敷き、素焼きと自家製タレで二度焼きしたことで「活」とした焼きアナゴを並べ、タレのボトルと奈良漬けとガリを添える。どうしても比べてしまう宮島口に及ばなくても、焼きの香りと煮アナゴのような柔らかさで、おいしいアナゴ丼。容器には高さがあるが、上げ底と上部の空間により、分量はひかえめ。価格は2004年時点で1,260円、2014年4月の消費税率改定で1,300円、2019年時点で1,400円、2023年時点で1,500円。
※2024年11月補訂:写真を更新し解説文を手直し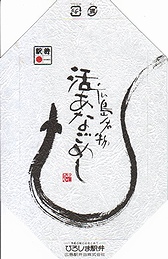

上記の駅弁「活あなごめし」の、2004年時点での姿。容器の素材と値段以外は、何も変わっていない。2004年度のJR西日本の駅弁キャンペーン「駅弁の達人」の対象駅弁であり、その応募シールがふたに貼られた。当時はアルカリイオン水とアナゴのエキスで炊いたコシヒカリの御飯と紹介された。
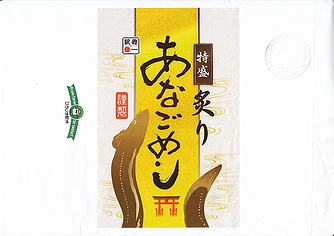

2019(令和元)年までに発売か。催事場での実演販売の専用商品かもしれない。広島駅の駅弁「炙りあなごめし」の、値段にアナゴと御飯の分量が約1.5倍になったもの。深い容器に中身を薄く敷いた見た目は特盛らしくなく、しかし食べるとアナゴに厚みと量があり、とろ〜り柔らかく、高価も食べて満足感。2020−2021年シーズンで終売か。
※2023年6月補訂:終売を追記

2016(平成28)年の秋にスーパーの駅弁催事で販売、2019(平成31)年1月の京王百貨店の駅弁大会と阪神百貨店の駅弁大会で実演販売。これ以外の時期や場所で売られたかどうかは分からない。四角い容器に白飯を詰め、商品名どおりの白焼き風炙りあなご3本15切れのみで覆う。つまり飯と穴子のみでできている、この上ないシンプルな内容。著名な宮島口駅弁とは明らかに違う、柔らかすぎて溶けていくこんな味もアリか。催事場では人気の商品になっていた。半年間ほどの販売か。
※2020年6月補訂:終売を追記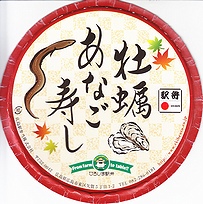

2019(平成31)年1月の京王百貨店の駅弁大会で実演販売。円形のプラ容器に酢飯を詰め、刻み海苔で覆い、炙りアナゴとカキ2個を置き、ニンジンと錦糸卵で彩る。これを定評の味の詰合せと見るか、やっつけ仕事と見るか。翌2020(令和2)年1月の阪神百貨店の駅弁大会にも出現した模様。
※2020年6月補訂:現況を追記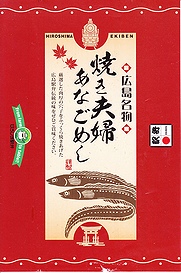

2018(平成30)年1月の京王百貨店の駅弁大会での実演販売でのみ販売か。その名のとおり、広島駅の駅弁「夫婦あなごめし」の“焼き”バージョン。タレ御飯に薄い焼アナゴ2本分が横たわり、高菜漬と柴漬けが添えられる。好みの問題だが、このほうが香りは増すと感じた。もし焼穴子駅弁ばかり食べていれば、通常版の煮穴子が恋しくなるかも。同年の夏頃に広島駅かどこかで買えたようで、あとはそれっきり。
※2020年6月補訂:終売を追記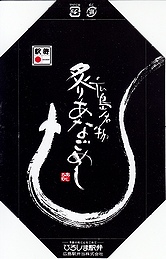

2016(平成28)年1月の発売か。従前の「炙りあなごめし」をリニューアルしたといい、ふたの色が白から黒に変わったが、味にも内容にも価格にも差異はみられない。半年ほどは、少なくとも首都圏での実演販売では、このパッケージで売られた模様。後に元の白い姿へ戻った。

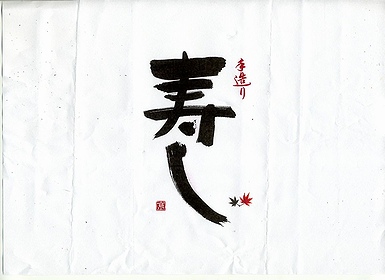

2008(平成20)年2月3〜8日に仙台の藤崎本店で開催された駅弁催事「全国駅弁大会とうまいもの市」で実演販売されていた商品。見てのとおり、太巻きが1本入るだけのシンプルな内容。しかしその中身や風味のほとんどが玉子焼であり、穴子は身こそ見えるものの風味はなし。現地に実態がないほうがよいと思う。
実演ブースの中で中国・韓国産穴子を焼いて切って詰める店員の手付きはどう見ても素人、手際の悪さで行列が進まず、十数人の来客をさばくのに1時間以上もかけられた。この年の京王百貨店の駅弁大会で広島駅弁の実演販売がなぜか中断され、2週目のチラシに穴を開けてしまったが、その理由がここにあるのかどうか。
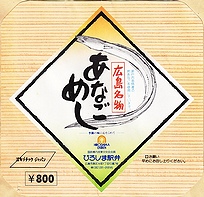
1980年代のものと思われる、昔の広島駅弁のふたの一部。瀬戸内海の沿岸では、昭和時代やそれ以前から、各地にアナゴの駅弁が存在した。